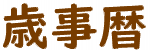暦の吉凶 十二直

十二直って何?
十二直(じゅうにちょく)は北斗七星の柄杓が季節によって指す方角を、十二支に割り当てたものです。
暦の真ん中あたりの欄に記載されているため、「中段」とも呼ばれます。
初めは北斗七星の柄杓の柄の指し示す方位によって季節を知るためのものでしたが、後に吉凶の要素も加えられました。
冬至の頃、日没後に北斗七星の柄杓の先端に当たる破軍星(はぐんしょう)が真北(子)を指すので、冬至の日を「建子の月(子のおざす月)」としました。
「おざす」とは、柄杓の先端が十二支のいずれかの方位を指しているという意味です。
古代中国では、冬至の日が太陽の運行の出発点(暦の起点)として重視されていました。
そこで、初めの建を十一月節の最初の子の日と決めました。
また中国では早くから北斗七星を神格化し、7つの星の一つ一つに人の運命を司る力があると考えられていました。
日本の十二直
日本では奈良時代の具注暦に、すでに記載されています。
江戸時代の仮名暦の、日の干支の下の欄(中段)に仮名で書かれていました。
そこにはいろいろな行動に、細かく吉凶が示されていました。
十二直に限らず明治以降の民間暦に載っている吉凶は、江戸時代のものが現代風にアレンジされています。
また単純化され、吉の日はすべて吉、凶の日はすべて凶と解釈されています。
十二直の配当は、旧暦の節入り日の干支と組み合わせて決められます。
節入り日は「おどる」といって必ず前日と同じ十二直になり、同じ十二直が並びます。
十二直の吉凶

現代では「建築吉日」として十二直の中から、たつ(建)、みつ(満)、たいら(平)、さだん(定)、なる(成)、ひらく(開)の6つが用いられています。
これらの日に地鎮祭や上棟式など、建築の重要な祭事が行なわれます。
建(けん たつ)
北斗七星の柄杓の先端が建(おざ)す日
万物を建て生ずる日
発起の一切が吉
最吉日。
大吉: 新しい衣を着る、柱を建てる、棟上げ、神仏祭祀、婚礼、開店、開業、移転、旅行、金銭授受、穀類収納、祝い事
凶: 動土、蔵開き、船に乗る
除(じょ のぞく)
万物を折衝して百凶を除き去る日
障害を取り除く日
一切解除の日
不浄を拭い、悪しきことを除ける日。
吉: すす払い、沐浴、治療開始、祭祀、不浄を払う、服薬、種まき、井戸掘り、仕事始め、物を捨てる事
凶: 婚礼、出行、見合い、夫婦交合、金銭の支出・賃貸、動土、勝負事
満(まん みつ)
天帝の蔵に天の宝を満たし、万物満ちあふれる日
万事の福が成就する日
充満の日
吉: 家造り、建築、婚礼、神仏祭祀、祝い事、旅行、開店、開業、移転、種まき、収納
凶: 動土、服薬始め、夜更かし、鍼灸
平(へい たいら)
天帝たちが集まって、人間に万物を平分する日
善悪共に平らかになる日
平安に鎮まる日
物事が平等円満に成立する日。
吉: 婚礼、引っ越し、道路修理、壁塗り、祝い事、相談事、柱建て、地固め、旅行
凶: 川・溝・穴を掘ること 動土、種まき
定(てい さだん)
何事を決定するにも善し
万事一切を定める日
必定の日
物事すべて定まってとどまる日。
将来の基礎を固める吉日。
吉: 家造り、婚礼、縁談、使用人を雇う、動土、祈祷する、種まき、売買契約、祝い事、開店、開業、移転、規則を制定する
凶: 訴訟、樹木の植え替え、旅行
執(しつ とる)
万物を執りたつ日
万事一切を取り始める日
ものを受け入れる日
万物の活動に育成を執行し促す日。
吉: 家造り、井戸掘り、種まき、婚礼、五穀収穫、神仏祭祀、移転、物の買い入れ、狩猟、祝い事、手に入れる事
凶: 出行、庫開き、多額の支出、勝負事、全て金銭その他を出すこと、訴訟
破(は やぶる)
この日戦えば必ず傷つくから破という
物事を衝き破る日
破壊の日
吉: 罪人を処刑する、出陣、漁猟、服薬、訴訟、談判事
凶: 開店開業、諸芸を学ぶ、建築、旅行、神仏祭祀、婚礼、祝い事、約束事、勝負事、物事の取り決め
危(き あやぶ あやう)
何事も自重が大切な日
厄が集約する
険悪の日
吉: 家造り、種まき、婚礼、酒造り、神の祭祀、木を切る
凶: 高いところに上る、旅行、登山、乗船、新しい事を始める、水辺の遊び
成(せい なる)
万事が成就するので始めるに吉
成就の日
吉: 婚礼、立願、入学、旅行、種まき、諸芸を学ぶ、金銭の借り入れ、新たに始めること、建築、柱立て、開店、仕込み、開業、移転、披露
凶: 訴訟、談判事
納・収(おさん)
万物を収斂する日
万物を取り納める日で、天倉ともいう
宝を蔵にしまう日
吉: 入学、婚礼、家造り、いろいろ買い納める、商品仕入れ、金銭借り入れ、五穀収穫・収納、移転植樹、集金
凶: 葬送、出行、鍼灸、神仏祭祀、大掃除、婚礼、見合い
開(かい ひらく)
天帝の使者が険難を開き、道が開ける日
万事一切を開くに吉
法蔵が戸を開ける日
吉: 諸芸を学ぶ、元服、婚礼、入学、就職、移転、種まき、商品仕入れ、普請、開店、井戸掘り、家づくり、蔵を開ける
凶: 葬式、不浄な事
閉(へい とづ とず)
陰陽の気が閉じ塞がって、通れない日
何事も閉止する日
法蔵の戸に鍵をかける日
万事一切が成就なし
吉: 建墓、墓標立て、池を埋める、穴を塞ぐ、金銭の収納、修繕、葬式
凶: 棟上げ、婚礼、開店、開業、祭事、祝い事、事始め