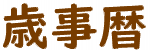十三夜
十三夜とは
十五夜(旧暦八月十五日)から約1ヶ月後の、旧暦九月十三日の夜の月をこう呼びます。
新暦ではだいたい10月から11月頃。

十五夜に対し「後(のち)の月」といいます。
中秋の名月の次に月が美しいとされ、古くから観賞する習慣があります。
十三夜は日本発祥の風習
中秋の名月を観賞する風習は中国から伝わりましたが、十三夜は日本発祥の行事です。
醍醐天皇の延喜19年(919年)の9月13日に観月の宴が催されたのが始まりとも、宇多天皇が十三夜の月を絶賛したのが始まりともいわれます。
八月の十五夜の月見をして九月十三夜には何もしないのは、「片見の月(片月見)」といって嫌われました。
十五夜の月見をしたら、必ず十三夜も月見をするものとされます。
十三夜も収穫の祭り
十五夜は、芋類の収穫の時期なので「芋名月」とも呼ばれます。
十三夜は、大豆と栗の収穫の時期なので、「豆名月」「栗名月」とも呼ばれます。
月見団子のほかに豆、栗、柿などを供えます。
いわゆる満月よりは少々欠けていますが、八月よりは秋が深まって空気も澄んできているので、満月でなくても美しく見えるのでしょう。
田舎から柿くれにけり十三夜
炭 太祇
後の月声を残して鳥ゆけり
高篠勇夫
月よりも雲に光芒十三夜
井沢正江