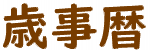暦の吉凶 下段
下段って何?
日々の暦の欄の下の方に記載されている暦注のことを、「下段」または「暦注下段」「暦の下段」と呼びます。

下段に書かれている内容は迷信的ではありますが、古くから庶民に根強く支持されてきました。
平城天皇の大同2(807)年に暦注が廃止されて官製の暦が発行されましたが、まったくの不評で、3年後に暦注が復活しました。
1000年経った明治5年(1872年)の改暦のさいにも廃止されましたが、「おばけ暦」という非公認の暦に引き続き記載され、生き残りました。
太平洋戦争中にも紙不足のため暦注付きの暦が廃止されましたが、戦後は自由に出版されるようになり、現代に至ります。
凶日・悪い日
下段は悪い日を避けるための生活の指針として伝わってきました。
平安時代初期の「枕草子」246段には凶会日が登場します。
黒日(くろび)
受死日(じゅしにち じゅしび)、辷日(まろぶひ)ともいい、●と記載されることも。
最低の大悪日、百事に慎むべき日。
この日はほかの暦注を見る必要がないといいます。
元日がこの日に当たると、行事はすべて翌日に繰り延べられたそうです。
物事が成就しがたく悪い結果を招くといい、この日に発病すれば、重病になるともいわれます。
凶: 病気見舞い、服薬、鍼灸、旅行
ただし葬式だけは差し支えありません。
| 正月 | 戌の日 |
|---|---|
| 二月 | 辰の日 |
| 三月 | 亥の日 |
| 四月 | 巳の日 |
| 五月 | 子の日 |
| 六月 | 午の日 |
| 七月 | 丑の日 |
| 八月 | 未の日 |
| 九月 | 寅の日 |
| 十月 | 申の日 |
| 十一月 | 卯の日 |
| 十二月 | 酉の日 |
十死日(じゅうしにち)
十死(じゅうし)、十し、十死一生日(じゅうしいっしょうび)、天殺日(てんさつび)とも。
黒日(受死日)に次ぐ凶日、すべての事に関して大悪日。
葬式、婚礼に用いると災難に遭うといいます。
昔、宝頂山の麓に住む久米という法王とその9人の息子が、全員酉・巳・丑の日に死んだことに由来するそうです。
| 正月 | 酉の日 |
|---|---|
| 二月 | 巳の日 |
| 三月 | 丑の日 |
| 四月 | 酉の日 |
| 五月 | 巳の日 |
| 六月 | 丑の日 |
| 七月 | 酉の日 |
| 八月 | 巳の日 |
| 九月 | 丑の日 |
| 十月 | 酉の日 |
| 十一月 | 巳の日 |
| 十二月 | 丑の日 |
五墓日(ごむにち ごむび)
五墓(ごむ)、五む日とも。
五行(木火土金水)の墓という意味。
陰陽五行思想では、十二支の丑・辰・未・戌には五行のうちの土性が配当されます。
日の干支が戊辰・丙戌・壬辰・乙丑・辛未に当たる日を五墓日といいます。
人が九星などと同じように生まれ持つ納音(なっちん)の、自分の性がこの日にあたった人のみ、すべて凶になります。
逆に、納音がこの日に当たっていない人には、何の影響もありません。
たとえば、平成元年生まれの人の納音は大林木で、木性です。
この人にとっては日の干支が乙丑に当たる日のみが五墓日で、ほかの日は何の障りもありません。
納音は市販の運勢暦に載っています。
この日に葬式を出すと墓を5つ並べることになるといわれ、近親で足りない場合は友人や遠縁まで集めて揃えるといいます。
凶: 土を動かす、地固め、開店、葬送、墓を作る、種まき、旅行、祈祷。
| 戊辰の日 | 土性の人は凶 |
|---|---|
| 丙戌の日 | 火性の人は凶 |
| 壬辰の日 | 水性の人は凶 |
| 乙丑の日 | 木性の人は凶 |
| 辛未の日 | 金性の人は凶 |
帰忌日(きこにち)
「きいみび」「きしにち」「きこじつ」とも読み、帰忌(きこ)、きこ日、きいみとも。
帰忌とは天棓星(てんぼうせい)(りゅう座のβ,γ,ζ,ν星)の精のことで、この精が下りてきて人家の門の前に陣取り、住人が帰宅するのを妨害する日を帰忌日といいます。
奈良時代(天平勝宝8歳)に正倉院に納められた具注暦に記載されているくらい、古い歴史を持ちます。
凶: 旅行先からの帰宅、里帰り、貸し出した物の返却、移転、金銭の貸し出し、嫁取りなど。
| 正月・四月・七月・十月 | 丑の日 |
|---|---|
| 二月・五月・八月・十一月 | 寅の日 |
| 三月・六月・九月・十二月 | 子の日 |
血忌日(ちいみにち)
「ちいみび」「ちこにち」、血忌(ちいみ)とも。
血忌とは梗河星(こうかせい)(うしかい座のρ,σ,ε星)の精で、古代中国ではこの3つの星を「殺忌」「日忌」「血忌」と呼び、殺伐の気を司るといわれます。
血忌日も具注暦に記載されている古い暦注です。
凶: 鍼灸、手術、死刑執行、狩猟、魚獣を殺すなど血を見ることや、奉公人の雇い入れ。
| 正月 | 丑の日 |
|---|---|
| 二月 | 未の日 |
| 三月 | 寅の日 |
| 四月 | 申の日 |
| 五月 | 卯の日 |
| 六月 | 酉の日 |
| 七月 | 辰の日 |
| 八月 | 戌の日 |
| 九月 | 巳の日 |
| 十月 | 亥の日 |
| 十一月 | 午の日 |
| 十二月 | 子の日 |
重日(じゅうにち)
「ぢう日」「じゅうび」「ちう日」とも。
日の十二支が巳の日(陽が重なる日)と亥の日(陰が重なる日)に当たります。
この日に行なったことは善悪に関わらず重なって生じるといわれ、吉事は良いが凶事には用いてはいけないとされます。
凶: 婚礼、治療、種まき、葬送、仏事、出家。
吉: 衣類の裁断や着初め、商品・不動産の買い入れ、初入学、預金。
復日(ふくにち)
「ぶくび」「ぶく日」とも。
重日と同じく、この日に吉事を行なえば吉が重なり、凶事をすれば凶が重なります。
凶: 婚礼、葬送。
吉: 旅行、金銭の貸し出し。
大吉: 善行。
| 正月・七月 | 甲と庚の日 |
|---|---|
| 二月・八月 | 乙・辛の日 |
| 三月・六月・九月・十二月 | 戊と己の日 |
| 四月・十月 | 丙・壬の日 |
| 五月・十一月 | 丁・癸の日 |
天火日(てんかにち)
天火(てんか)、「てんかび」「五貧日」とも。
陰陽五行説では火を天火、地火、人火に分けますが、そのうちの天火は「天の火気がはなはだしい」という意味を持ちます。
凶: 棟上げ、屋根葺きをすると必ず火災に遭う。ほかに家屋の修造、引っ越し。
他のことには障りなし。
| 正月・五月・九月 | 子の日 |
|---|---|
| 二月・六月・十月 | 卯の日 |
| 三月・七月・十一月 | 午の日 |
| 四月・八月・十二月 | 酉の日 |
地火日(じかにち)
地火(じか)、「ちかび」とも。
天火日に対するもので、「大地の火気がはなはだしい」という意味を持ち、地気炎上の凶日とされます。
凶: 柱建て、井戸掘り、地ならし、礎石据え、種まき、墓を築く、葬送など土を動かすこと。
| 正月 | 巳の日 |
|---|---|
| 二月 | 午の日 |
| 三月 | 未の日 |
| 四月 | 申の日 |
| 五月 | 酉の日 |
| 六月 | 戌の日 |
| 七月 | 亥の日 |
| 八月 | 子の日 |
| 九月 | 丑の日 |
| 十月 | 寅の日 |
| 十一月 | 卯の日 |
| 十二月 | 辰の日 |
三箇の悪日
三箇(さんが)とは、三神(貧窮・飢渇・障碍)と三毒(貪欲・瞋恚・愚痴)を表わし、万事に用いてはならないとされます。
とくに、仏事と葬儀は避けます。
江戸時代にはとても強く信じられていた暦注です。
人の生まれ年の干支によって、三箇の悪日に当たる日は異なります。
たとえば、平成元年生まれの人の干支は巳です。
巳年生まれの人は、節切りの四月の申の日が大禍日、酉の日が狼藉日、寅の日が滅門日なので凶日です。
しかし市販の運勢暦のなかには、生まれ年に関係なく日の干支が該当する日を凶日とするものがあります。
| 忌み月 | 大禍日 | 狼藉日 | 滅門日 | |
|---|---|---|---|---|
| 寅年生まれ | 正月 | 亥の日 | 子の日 | 巳の日 |
| 卯年生まれ | 二月 | 午の日 | 卯の日 | 子の日 |
| 辰年生まれ | 三月 | 丑の日 | 午の日 | 未の日 |
| 巳年生まれ | 四月 | 申の日 | 酉の日 | 寅の日 |
| 午年生まれ | 五月 | 卯の日 | 子の日 | 酉の日 |
| 未年生まれ | 六月 | 戌の日 | 卯の日 | 辰の日 |
| 申年生まれ | 七月 | 巳の日 | 午の日 | 亥の日 |
| 酉年生まれ | 八月 | 子の日 | 酉の日 | 午の日 |
| 戌年生まれ | 九月 | 未の日 | 子の日 | 丑の日 |
| 亥年生まれ | 十月 | 寅の日 | 卯の日 | 申の日 |
| 子年生まれ | 十一月 | 酉の日 | 午の日 | 卯の日 |
| 丑年生まれ | 十二月 | 辰の日 | 酉の日 | 戌の日 |
大禍日(たいかにち)
大禍(たいか)、「大くわ」とも。
もっとも悪い日、大凶悪日とされます。
口舌を慎み、家の修理、門戸を建てること、船旅、葬送などは固く忌まれる日です。
この日に人を訪問すると口に災いが生じるとか、この日に始めたことはのちに争いを起こすなどといわれます。
狼藉日(ろうしゃくにち)
狼藉(ろうじゃく)とも。
万事に凶で、この日を用いると百事みな失敗するといわれます。
滅門日(めつもんにち)
滅門(めつもん)とも。
大悪日で何事も成就しないといわれます。
もしもこの日に新しい事をすると、一家一門みな滅ぶとされます。
時下食(ときげじき)
「下食時(げじきどき)」とも。
ある特定の日の特定の時間(一辰刻)のみを忌みます。
天狗星(てんこうせい)の精が下りてきて食事をする時間のことをいい、この時間に人間が食事をすると天狗星の精に食べ物の栄養をみな吸い取られてしまうため、この時間の飲食を忌むといいます。
凶: 種まき、沐浴、草木を植えること。
歳下食(さいげじき)
「さい下じき」とも。
天狗星の精が食事をする日のこと。時間は関係ありません。
天狗星の精は60日目に1日、1年に6日地上に降りてきて終日終夜食事をします。
軽い凶日なので、ほかの暦注の吉日に重なれば忌む必要はないとされます。
逆に凶の暦注と重なると、大凶になります。
凶: 大食、大酒、種まき、草木を植えること。
この日に食あたりをすると、長患いになるか死に至るといわれます。
凶会日(くえにち)
「くえび」「凶会(くえ)」「くゑ日」とも。
陰と陽の気の調和がうまくいかない日なので、万事に忌むとされます。
悪魂が集会する日ともいわれます。
この日に吉事を行なうと、凶事に転換されてしまいます。
凶: 婚礼、神仏祭祀、旅行、種まきなど何事も凶
『枕草子』に記述があります。
第246段 ことに人に知られぬもの
凶会日。人の女親の老いにたる。
(格別人に気にされないもの
凶会日。他人の母親の年をとったの。)
「枕草子」が書かれた時代に用いられていた宣明暦には、凶会日は年に82日あったそうです。
しょっちゅうやってくるうえに、あまり信じられていなかったようです。
凶会日は月ごとに特定の干支の日を当てはめます。
下の表は貞享暦で整理されたものです。
| 正月 | 辛卯・甲寅 |
|---|---|
| 二月 | 己卯・乙卯・辛酉 |
| 三月 | 甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・壬申・戊申・庚辰・甲申・丙申・甲辰・庚申 |
| 四月 | 戊辰・辛未・癸未・乙未・己亥・丙午・丁未・戊午・己未・癸亥 |
| 五月 | 丙午・戊午 |
| 六月 | 己巳・丙午・丁未・丁巳・己未 |
| 七月 | 乙酉・甲辰・庚申 |
| 八月 | 己酉・乙卯・辛酉 |
| 九月 | 甲戌・辛卯・壬辰・癸巳・甲午・乙未・丙申・丁酉・戊戌・庚戌・甲寅 |
| 十月 | 乙丑・己巳・丁丑・戊子・己丑・戊戌・己亥・辛丑・壬子・癸丑・丁巳・癸亥 |
| 十一月 | 戊子・丙午・壬子 |
| 十二月 | 戊子・丁未・壬子・癸亥 |
往亡日(おうもうにち)
「おうぼうじつ」「往亡(おうもう)」「わうまう」とも。
生きて滅ぶという凶日。
凶: 遠出、移転、婚礼、旅行、神社仏閣への参拝など。
往亡日に当たる日は、各月の節から節入りの日を含めて何日目として決めます。
| 正月 | 7日目 |
|---|---|
| 二月 | 14日目 |
| 三月 | 21日目 |
| 四月 | 8日目 |
| 五月 | 16日目 |
| 六月 | 24日目 |
| 七月 | 9日目 |
| 八月 | 18日目 |
| 九月 | 27日目 |
| 十月 | 10日目 |
| 十一月 | 20日目 |
| 十二月 | 30日目 |
吉日・良い日
古くから伝わってきた吉日は、天赦日と大明日の二つだけでした。
宝暦5年(1755年)、土御門(安倍)泰邦が宝暦暦を編纂するにあたり、天恩日・母倉日・月徳日を書き加えました。
これ以降、吉日が増えていきました。
天赦日(てんしゃにち)
「てんしゃび」「天しゃ」「天しや」とも。
百神が天に昇る日で、天が地上の万物を育て養って罪を赦す日です。
天の恩恵により最上の大吉日で、とくに婚礼、開店、新事業開始、拡張などに大吉。
ほかの凶日と重なっても、何の障害も起こらない吉日です。
- 立春より後の戊寅の日
- 立夏より後の甲午の日
- 立秋より後の戊申の日
- 立冬より後の甲子の日
神吉日(かみよしにち)
「かみよしび」「神よし」「上吉」とも
万事、神事に関することに吉とされる日です。
日本独自の暦注。
吉: 神社の参拝、祭礼、神棚造り、祖先の祀りなど。
凶: 不浄のこと
神吉日は日の干支だけで決まります。
- 乙丑・丁卯・己巳・庚午・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・乙酉・戊子・辛卯・甲午・丙申・丁酉・己亥・庚子・辛丑・癸卯・乙巳・丙午・丁未・戊申・己酉・辛亥・壬子・乙卯・戊午・己未・庚申・辛酉・癸亥
大明日(だいみょうにち)
「大明(だいみょう)」「大みやう」とも。
天地開通して、すみずみまで太陽が照らして大きく開ける日で、大吉日。
唐の時代の大明暦に初めて記載されました。
すべての吉事、善行によく、とくに婚姻、移転、旅行、建築、造作、開店、開業にいいとされます。
ほかの凶日と重なると、中吉の日になります。
大明日も日の干支だけで決まります。
- 戊午・己巳・庚午・辛未・壬申・癸酉・丁丑・己卯・壬午・甲申・丁亥・壬辰・乙未・壬寅・甲辰・乙巳・丙午・丁未・己酉・庚戌・辛亥・丙辰・己未・庚申・辛酉
鬼宿日(きしゅくにち)
「鬼宿」「きしゅくび」とも。
二十八宿の中の最大吉日です。
とくに名誉、長寿を祝うのに最上の日で、火の神を祀るのにもいい日です。
吉日のなかでも格が高く朝廷・公家や武家の公事に用いられたため、庶民は婚礼に用いることだけは遠慮したといいます。
鬼宿日に当たる日は二十八宿の鬼宿と同じです。
28日周期で回ってきます。
天恩日(てんおんにち)
「天おん」とも。
『簠簋内伝(ほきないでん)』の「七箇の善日」のうちのひとつ。
天の恩恵により、万物が成育して福徳が得られる日です。
吉事に用いて大吉だが、凶事には用いてはならないとされます。
吉: 昇進、婚礼、屋根葺き、種まき、就職、家督を譲るなど。
ほかの凶日と重なった場合、半吉になる、小悪日なら天恩日が勝るから妨げなし、黒丸日と十死日以外は障りなし、などといわれます。
天恩日になる日の決め方には諸説あります。
賀茂在方の「暦林問答集」によると、以下の通りです。
- 甲子・乙丑・丙寅・丁卯・戊辰・己卯・庚辰・辛巳・壬午・癸未・己酉・庚戌・辛亥・壬子・癸丑
母倉日(ぼそうにち)
「母倉(ぼそう)」とも。
『簠簋内伝(ほきないでん)』の「七箇の善日」のうちのひとつ。
母が我が子を思うように天が万物を憐れむ日。
地の恵みにより万物が成育して繁栄する日です。
とくに婚礼が大吉。
吉: 普請、造作、開業。
ほかの凶日と重なっても忌むことなしの日ですが、二月の亥の日は重日と重なるので、葬儀は避けたほうがよいといわれます。
| 正月・二月 | 子の日・亥の日 |
|---|---|
| 三月・六月・九月・十二月 | 巳の日・午の日 |
| 四月・五月 | 寅の日、卯の日 |
| 七月・八月 | 丑の日・辰の日、未の日、戌の日 |
| 十月・十一月 | 申の日、酉の日 |
月徳日(つきとくにち)
「げっとくにち」「がっとくにち」「月とく」とも。
『簠簋内伝(ほきないでん)』の「七箇の善日」のうちのひとつ。
その月の福徳を司る日です。
万事障りのない日で、家の増改築、土に関わること、婚礼、種まきに吉日です。
とくに女性にとって良い日。
| 正月・五月・九月 | 丙の日 |
|---|---|
| 二月・六月・十月 | 甲の日 |
| 三月・七月・十一月 | 寅の日、卯の日 |
| 七月・八月 | 壬の日 |
| 四月・八月・十二月 | 庚の日 |