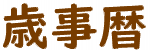鏡開き
1月11日。
正月にそなえた鏡餅を下げて食べる行事。
古くは正月二十日に行われていました。
武具に供えた餅(具足餅)を下ろして雑煮にすることを「刃柄(はつか)を祝う」と呼んでいたので、二十日でした。
また、女性は二十日に鏡台に供えていた餅を下ろして「初顔(はつかお)祝う」といっていました。
しかし、徳川三代将軍家光が他界したのが20日だったため、11日に変更されたまま今日に至っているといわれます。
そもそも武家社会での習わしなので、鏡餅を刃物で「切る」のは縁起が悪いと、手や木槌などで叩いて割って「開く」と言い換えられました。
正月の年神さまのお下がりの固い餅をいただく習わしが、正月に固いものを食べて延命長寿を祈った「歯固め」と結びついて現在の形になりました。
砕いた餅はしる粉やぜんざい、雑煮にして食べられます。