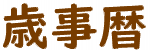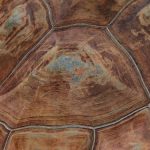暦の吉凶 方位神

方位神ってなに?
方位神とは、九星術で得られた方位の上を毎年十干や十二支に従って移動する神々のことで、吉神と凶神に分けられます。
その年の方位神の位置は、市販の運勢暦の初めの方のページにある「方位吉凶図」に書かれています。
方位は引っ越し、家の建築、旅行、買い物などをするさい、自分の家を中心としてどの方角が吉方位(凶方位)かを見るときに用います。
この記事は、「方位吉凶図」の各方位神の説明です。
吉神と吉方位
吉方位にいる吉神は、歳徳神・太歳神・歳禄神の3つが代表的です。
ただし、太歳神は場合によって凶神の作用が働くことがあります。
普請造作、家屋新築、動土、移転、開店、旅行、結婚などを行なうさい、まず年月日から吉神の所在を調べます。
そしてその方位に向かって執り行なうと良い結果が得られるといいます。
歳徳神(としとくじん)
暦を開くと、たいてい八角形の「方位吉凶図」の近くに描かれている女神さまです。
その年の福徳を司る神さまで、「年徳」「歳神」「お正月さま」「としとくさま」などと呼ばれます。
正月に門松を立てたりして家の中に迎えるのは、この神さまです。
「方位吉凶図」に「恵方」や「あき方」「明きの方」と書かれているのは歳徳神がいる吉方で、この方向の神社仏閣へ初詣(恵方参り)をすれば、その1年は安泰で家業繁盛するとされます。
何事も、この方向へ向かって行なえば成就するといいます。
恵方巻を丸かぶりするために向かう方角も、この方向です。
九星の自分の本命星(ほんめいせい)と歳徳神のいる方位が重なると、その年は大吉とされます。
暦によっては、歳徳神を牛頭天王の妃の頗梨采女(はりさいじょ)とするものがあります。
恵方(えほう)
恵方とは「あきの方」ともいわれ、その年に歳徳神が所在する方位のことです。
昔は歳徳神が来臨する方角をさしましたが、のちに上のような意味に変わりました。
この方位はすべてのことに大吉です。
さらに、その人の九星の本命星と同一になると、いっそう吉になるといわれます。
しかし、金神や歳破神などの凶神と同じ位置になると、凶方位に変わります。
恵方はその年の十干で決まります。
| 甲・己の年 | 甲(寅・卯の中間 東北東と真東の間) |
|---|---|
| 乙・庚の年 | 庚(申・酉の中間 西南西と真西の間) |
| 丙・辛の年 | 丙(巳・午の中間 南南東と真南の間) |
| 丁・壬の年 | 壬(亥・子の中間 北北西と真北の間) |
| 戊・癸の年 | 丙(巳・午の中間 南南東と真南の間) |
太歳神(たいさいじん)
(「八将神」のところで説明しています。)
歳禄神(さいろくしん)
1年間の吉福をつかさどる吉神です。
その年の十干に従い、十二支に位置します。
この方向に向かって普請・動土・旅行・結婚・開店・商取引・相談事などを行なうとすべて成就し、大成功を収めるといいます。
歳枝徳(さいしとく)
吉方位の一つ。
災いを救い、弱きを助ける吉神といい、万事に吉とされます。
太歳神の方位から5年先の十二支の方位に位置します。
歳徳合(としとくごう)
吉方位の一つ。
歳徳神と並ぶ吉神で、万事に吉で忌むことがないといわれます。
歳徳神の陽(剛)に対して歳徳合は陰(柔)で、私的なことや内輪のことにとくに吉です。
天徳(てんとく)
吉方位の一つ。
この方向に向かって物事を起こせば福を招き、運を開く吉方です。
万物の育成に徳があり、すべてにおいて大吉です。
六大凶殺以外の凶神なら、重なっても打ち消して吉とします。
天徳合(てんとくごう)
天徳よりも格が一枚下の吉方位です。
月徳合と性質が同じです。
多くの凶殺を解消し、この方向に向かって事を起こすと、幸福が得られるといいます。
月徳(げっとく)
大吉の方位。
その月の福を司り、凶殺を制し福をもたらします。
月徳合(げっとくごう)
吉方位の一つ。
百事に用いて吉とされ、多くの福が集まる吉方位で、多くの悪が解消される方位といわれます。
天道(てんどう)
吉方位の一つ。
天地自然の理に則し、結婚・移転・旅行などすべてに大吉とされます。
天徳・月徳と同じ方位にあると、さらに吉が増すといわれます。
生気(せいき)
「生気方(せいきかた)」の略で、吉方位の一つ。
万物の生成化育の恩恵を得ることができ、この方位に向かって座ったり寝起きすると、病難を避けられるといいます。
また、医薬を求めるのも吉です。
奏書(そうしょ)
吉方位の一つ。
つねに太歳神の身近にあり、善事を行なうと大吉です。
ただし、動土は凶です。
博士(はくし)
「はかせ」とも読み、吉方位の一つ。
奏書の反対の方位に位置します。
万事に良しとされます。
しかし、動土・植木・造営・井戸掘りには凶です。
凶方位にいる凶神
年の凶方には、「神殺(しんさつ)」と「方殺(ほうさつ)」の2つがあります。
神殺とは八将神・金神・その他の凶神が位置する方角のことです。
方殺とは凶となる方位のことで、本命殺・本命的殺・五黄殺・暗剣殺・歳破・月破の6つの凶方神を「六大凶殺」と呼びます。
江戸時代から暦に記載されるようになり、庶民の間で大流行したそうです。
[神殺] 金神(こんじん)
金神は金星(太白星)の精で、歳徳神の正反対に位置します。
戦争や大火・干ばつ・疫病を司る凶神です。
金神は古い暦には記載されていませんでしたが、平安時代末期から流行し始め、江戸時代の貞享暦に記載されるようになりました。
金神のいる方位は金の気が満ちて、物心すべてが冷酷になります。
昔は鬼門以上に忌み嫌われました。
この方位に向かって、動土・建築・移転・結婚・墓を作ることなどが厳しく忌まれました。
もしもこれを犯すと、「金神七殺(こんじんしちさつ)」といって家族7人が殺されるとされました。
家族に7人いないと、隣の家にまで災禍が及ぶとされて恐れられました。
金神は八将神のうちの大将軍と同じく、ときどき自分の方位から移動(遊行(ゆぎょう))します。
決まった十干十二支の日と、四季ごとに年間合計45日間留守にするので、その日は遊行先の方位さえ避けたら何事もだいじょうぶとされます。
また「金神の間日(まび)」という、金神がいるにも関わらずその方位に向かって何かをしても差し支えない日もあります。
九星の吉星である一白・六白・八白・九紫か、天徳・月徳・天道の吉神が巡る月も、吉神が凶神を押さえ込む(制化)ので金神の心配はありません。
[神殺] 巡金神・大金神・姫金神
金神は巡金神(めぐりこんじん)とも呼ばれます。
大金神はその年によって方位が一定していて、殺伐を司る大凶神です。
すべてのことに凶で、とくにこの方位に向かっての普請・修繕・動土・移転は忌まれます。
姫金神はつねに大金神の正反対の方位に位置し、大金神ほどの凶神ではありませんが同じ性質を持ちます。
病難、盗難などに注意が必要とされます。
[神殺] 八将神(はっしょうじん)
八将神は、それぞれ「方位吉凶図」の8つの方位に位置し、その方向の吉凶を司ります。
八大方位神ともいいます。
八将神は兄弟神で、父は牛頭天王、母は頗梨采女とされています。
太歳神(たいさいじん)
太歳神は木星(歳星、おおどし)の精とされ、四季の万物の成育を司る吉神。
代表的な3つの吉神のうちの一つでもあります。
その年の十二支の方位と同じ方位にいて、1年間、その方位を吉方とします。
しかし、木の精なので、太歳神が座する方向へ向かって樹木を伐採したり、草木を刈り取ると凶神に変化します。
また、訴訟事や談判、取り壊しなど破壊的な行為も大凶です。
反対に、結婚や家を建てること、開店や取引の始め・雇用・祝い事など建設的な行為は吉で、植え付けなどは大吉です。
大将軍(だいしょうぐん)
大将軍は金星(太白星)の精で、殺戮を司るといわれ、八将神の中でもっとも恐れられています。
大将軍は一つの方位に3年とどまって動かないため、「三年ふさがり」といわれます。
自宅から見て大将軍が座する方位に向かって建築・移転・土を動かす・結婚・出産・仏事などをすると、大けがや大病を患い3年のうちに死ぬなどとされます。
とくに旅行は大凶です。
しかし、春夏秋冬と土用にそれぞれ5日間だけ他の方位に移動(遊行)して留守をするので、その間は支障がないとされます。
また、方違えをしてこの方位を用いることもできます。
大陰神(だいおんじん)
大陰神は土星(鎮星)の精で、八将神の中の唯一の女神です。
太歳神の妃なので、太歳神の後を3年遅れて移動します。
陰事を司る凶神です。
大陰神が座する方位で学問や芸術に関することを行なうのは大吉です。
しかし、縁談や出産など女性に関すること一切が凶です。
歳刑神(さいぎょうしん)
歳刑神は水星(辰星)の精です。
土地を守護する神であり、刑罰・殺伐を司る凶神でもあります。
歳刑神のいる方位に向かって種まき・伐採・植え替え・動土は凶とされるため、農家にはとくに注意されていました。
反対に、破壊的な行為・武芸習得、刀剣や刃物の購入は吉です。
ただし、人の道や天の道に外れていないことが大前提です。
歳破神(さいはしん)
歳破神は大陰神と同じく土星の精です。
つねに太歳神の反対側にいて衝き破られることから、歳破神との名が付きました。
六大凶殺の歳破と同一で、大陰神の親戚に当たるといいます。
死亡と盗賊を司る凶神です。
歳破神は太歳神に剋され続けるため、歳破神の座する方位は凶とされます。
歳破神のいる方位へ向かっての普請・造作・動土・引っ越し・結婚・旅行・家畜を購入することは凶とされています。
もしもこれを犯すと、その家の主人が盗難などの祟りに遭うといわれます。
歳殺神(さいせつしん)
歳殺神は金星(太白星)の精です。
殺気を司り、万物を滅する凶神です。
大将軍の親戚に当たるといいます。
歳殺神のいる方位に向かっての結婚・出産・養子縁組・移動・建築・旅行・金策・習い事始めは凶とされます。
とくにこの方位に向かっての嫁取りと出産は大凶です。
もしもこれを犯すと、子孫と家畜が傷つけられるといわれます。
しかし、仏事は吉とされます。
黄幡神(おうばんしん)
黄幡神は羅睺星(らこうせい)の精で、太歳神の墓といいます。
羅睺星は想像上の天体で、光を覆って月食や日食を起こす星とされます。
土を司る凶神で、仏教での本地は摩利支天王ともいいます。
黄幡神のいる方位へ向かっての建築・移転・井戸掘りなど土地や土に関わる事柄・金銭の授受などは凶とされます。
しかし、武芸始め(弓始め)としてこの方位へ向かって弓を射るなど、武芸に関することは大吉とされます。
豹尾神(ひょうびしん)
豹尾神は、想像上の天体の計都星(けいとせい)の精です。
不浄を嫌うとされ、豹尾神の居座る方位で排泄をしたり、ペットや家畜を購入すると「子孫六畜(しそんりくちく)」といって家族6人すべてが傷つけられるとされます。
家族が6人いなければ、ペット・家畜、近親者にも及びます。
豹尾神は黄幡神と反対の方向に位置します。
[方殺] 本命殺(ほんめいさつ・ほんみょうさつ)
その人の本命星(ほんめいせい)が位置する方位のことです。
本命星とは、九星気学において、自分の生まれた年の九星図(年盤)の中央にある星です。
この本命星が、年・月・日のいずれでも在泊している方位を凶方位とみなします。
この方位に向かって、普請・造作・修理・動土・樹木の伐木や植え替え・婚姻・旅行・移転すると、必ず何らかの災厄を蒙るといいます。
また、この方位を犯すと健康を害するともいいます。
[方殺] 本命的殺(ほんめいてきさつ)
的殺(てきさつ)ともいいます。
年・月・日のいずれでも、本命星が位置する方位と正反対側の方位のことです。
この方位を犯すと、本命殺と同様の災厄を蒙るといいます。
しかし、この方位に相生の星があると災厄は比較的軽くなります。
逆に相剋の星があると倍増するそうです。
本命殺・的殺ともにその人の健康に影響を持つとして、この方位で病院や医師を探すのは慎重を期するべき、とする暦もあります。
本命星が「方位吉凶図」の中宮(真ん中)に入った場合、的殺はなくなりますが「八方塞がり」となって万事慎む必要が生じます。
[方殺] 五黄殺(ごおうさつ)
その年の八角形の「方位吉凶図」において、五黄土星が位置している方位のこと。
本来、五黄土星は中宮(八角形の真ん中)に位置して広大な大地の徳を備えているのですが、9年に1度、真ん中から外に出ます。
その出た方角が凶方となります。
五黄殺はいかなる吉神の力も撃破してしまうくらい強烈とされています。
吉神がいる方位なのに、吉になりません。
そのため、この方位に向かって何かをするのはすべて凶です。
とくに、土を動かすこと・引っ越しは大凶とされます。
もし誤ってこれを犯してしまうと、重くすると主人の生命にかかわり、軽く済んでも家人が害を蒙るのでできるだけ回避することが必要といいます。
[方殺] 暗剣殺(あんけんさつ)
五黄殺の正反対側に当たる方位で、暗闇の夜に不意に背後から斬りつけられるくらいに大凶の方位とされます。
五黄殺と同じく、いかなる吉神の力も撃破してしまうくらい強烈で、吉神がいても吉方位にはなりません。
もしもこの暗剣殺を犯すとさまざまな災厄が降って湧いて襲ってくるといわれ、とくに家の中で深刻な問題をもたらすとされます。
したがって、この方位に向かっての婚姻・普請造作・動土・修理・伐木や植え替え・移転・旅行・商取引などは厳しく慎むべきとされます。
五黄が中宮(八角形の真ん中)にいるときは、暗剣殺はありません。
[方殺] 歳破(さいは)
その年の十二支と反対側の方位のことです。
上で説明した八将神のうちの歳破神と同一の凶方で、土星の精です。
いかなる吉神の力も撃破してしまい、乗船・転居・旅行・動土・普請・結婚などを忌むのも歳破神と同じです。
もしもこれを犯すと、損害・紛争・破綻の害を蒙るといいます。
[方殺] 月破(げっぱ)
その月の十二支と反対側の方位のことです。
歳破と同じで、いかなる吉神の力も撃破してしまうため乗船・転居・旅行・動土・普請・結婚などを忌み、もしもこれを犯すと、損害・紛争・破綻の害を蒙ります。
そのほかの凶方位・凶神
八角形の「方位吉凶図」の中に、小さな文字で書かれている凶神の説明です。
六大凶殺よりは格が下がるため、凶意も少し軽くなります。
鬼門(きもん)
東北の方角(艮(うしとら))のことで、方位神のように移動しません。
鬼が出入りする不吉な方角として、すべてのことにおいて忌み嫌われています。
江戸時代の暦には、鬼門の方向へ向けての引っ越しや造作は忌むべきと書かれていました。
そこで、家の東北の方向に鬼門除けといわれる神仏を祀ったり、樹木を植えたりして、鬼が家の中へ出入りしないようにしました。
鬼門除けには、現在の京都御所で見られるように、猿の置物を屋根に置いたりします。
植物は、難を転じるという南天や、棘のあるヒイラギ、邪気を祓う桃の木を植えるといいといわれます。
鬼門と反対側、南西の方角(坤(ひつじさる))を裏鬼門(うらきもん)といいます。
鬼門同様に忌み嫌われますが、鬼門ほど強烈ではないそうです。
都天殺(とてんさつ)
都天(とてん)とも。
五黄殺に次ぐ凶方位とされます。
この方位に向かって、何事においても注意が必要といいます。
白虎(びゃっこ)
白虎神とも。
神殺の姫金神と同格の凶方です。
殺伐の気が盛んで、この方位に向かっての動土・普請を忌むべきといいます。
また白虎は血の神で、出産を司ります。
死符(しふ)
前年の歳破神の後に位置する凶神です。
歳破神の影響が翌年まで残るため、災いが生じるといいます。
この方位に向かって動土・塚や墓を建てることを避けるべきとされます。
病符(びょうふ)
前年の太歳神の後に位置する凶神です。
太歳神の影響が翌年まで残るため、災いが生じるといいます。
この方位に向かって新規に事を始めると、病気や災害を蒙るとされます。
劫殺(ごうさつ)・災殺(さいさつ)
ともに歳破に次ぐ凶方で、この方位に向かっての普請造作・修理・動土は凶とされます。
もしもこれを犯すと強盗や殺傷の災いがあるといいます。
蚕室(さんしつ)
八将神のうちの大将軍の后といわれる凶神で、大将軍と似ています。
この方位に向かっての動土や桑の葉の収穫を忌むべきとされます。
年の十二支によって方位を変えます。
小児殺(しょうにさつ)
小月建とも。
小児(学童前まで、10歳未満、数え12歳以下、など諸説あります)にのみ適用される、月の凶方位です。
これを犯すと、家族のなかの小児に災いが降りかかるといいます。
小児殺が「方位吉凶図」の中宮にあるときは、修理・造作・改築などに注意が必要とされます。