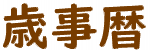初節句

初節句って何?
子どもが産まれて初めて迎える節句のこと。
節句はもともと「節供」と書き、「節」は1年のうちの特定の日のこと、「供」は神さまに供えた食べもののことです。
すなわち、節供は1年のうちの決められた日に、神と人とがともに食事をすることで、年に五つの節供があります。
そのうち、女児は3月3日の「上巳(桃)の節句」、男児は5月5日の「端午の節句」です。
初節句に何をするの?
初節句は、子どもの誕生を祝い、健やかな成長と将来の幸せを祈る行事です。
祖父母や親族を招き、祝い膳を囲みます。
かつて、長男・長女が生まれた場合のみ、お祝いをいただいた親戚を招いてとくに盛大にごちそうをふるまう風習がありました。
現在は2人目、3人目のときも同じようにお祝いします。
もしも、初節句が生まれて間もない、首も座っていないような時期だった場合は、無理せず翌年にまわしましょう。
初節句はどう祝うの?
女の子の桃の節句の場合、ひな人形を飾り、ひな壇に菜の花やひし餅、白酒、桃の花などを飾ります。
お祭りの仕方については当サイトの「ひな祭り | 歳事暦」で、節句の由来は「上巳の節句 | 歳事暦」にてそれぞれ説明しています。よろしければ合わせてお読み下さい。
男の子の端午の節句の場合、外飾りとして家の外に鯉のぼり、内飾りとして鎧兜や武者人形を飾ります。
ちまきや柏餅を用意し、菖蒲の葉を軒下に吊るしたり、菖蒲の葉を入れた風呂に入ったりします。
端午の節句の由来は「端午の節句 | 歳事暦」で詳しく説明しています。
祝い膳の内容は?
桃の節句の場合、手鞠寿司かちらし寿司に、はまぐりのお吸い物が定番です。
春野菜の小鉢や焼き魚、貝類のぬた(てっぱい)、祝い酒として白酒を添えます。
そこにひし餅やひなあられ、よもぎ餅などを準備します。
端午の節句の場合、巻き寿司や赤飯を中心にしておかずを添えます。
柏餅やちまきも準備して、「こどもの日」なので子どもの好きなものを並べましょう。
節句のお飾りは、どちらの実家が贈るの?
昔は母方の実家から、ひな人形や鎧兜が贈られるしきたりがありました。
しかし、従来のしきたりにのっとると、帯祝いの岩田帯に始まって、お宮参りの晴れ着、お食い初めの食器、七五三の晴れ着と、すべてお母さんの実家の負担になってしまいます。
孫がかわいいのはお父さん側の実家も同じなので、現代では両家で折半するのが一般的になっています。
もしも両家とも用意してくれる場合、一緒に買いに行ったりお祝い金だけもらったりして、どちらかだけということのないようにします。
初節句のお飾りは何を買えばいいの?

現代は核家族で住宅の事情もあり、ひな人形も鎧兜も大きな壇飾りではなく、親王飾りや兜だけをガラスケースに入れたものに人気があります。
また、女の子には博多人形や鼓を持った日本人形、男の子には金太郎人形や桃太郎人形などが贈られたりもします。
古来、節句の人形にはその子にふりかかった「厄」を身代わりとなって引き受ける役目があるので、1人に一つがよいといわれます。
お母さんや兄弟姉妹との兼用、親戚などからの譲り受けはよくありません。
小さくても、その子だけのものを用意します。
ただし、鎧兜の具足飾りや武者人形は数を増やさないものとされているので、2人目以降は武者の絵や掛け軸を用意します。
しかし現代は「厄」の意識が変化しており、きょうだいで共有することに抵抗感を持たれなくなってきているようです。
八朔節句
女の子は3月3日、男の子は5月5日の男女別ではなく、旧八月朔日に男女一緒に初節句を祝う地域があります。
長男は藁で作った馬、長女は「団子雛(だごびーな)」という米の団子で作ったひな人形を座敷に並べて飾り、子どもの成長を祈ります。
この馬やひな人形は翌日、近所の子どもさんたちに配ります。
初節句の包み

- 祝儀袋、熨斗紙
- 水引 紅白の蝶結び
- 熨斗 あり
- 表書き 「祝初節句」「御祝」など
- 金額 親族は5000円~1万円、知人は3000円~5000円
もしも鯉のぼりやひな人形などを贈る場合は、数ヶ月前から1ヶ月前までに。
現金や商品券の場合は、半月前から当日までに贈ります。
親族や親しい人からのお祝いは、人形や玩具、衣服などを贈ります。
お祝いをするのは初節句のときだけです。
初節句のお返し
初節句はとくに内祝が必要ではありません。
もしも贈るなら、いただいた金額の2分の1から3分の1の品物を。
祝儀用の紅白の砂糖などの詰め合わせに、菱餅や柏餅などを添えるのもよいでしょう。

- 熨斗紙
- 水引 紅白の蝶結び
- 熨斗 あり
- 表書き 「内祝」「桃の花」「菖蒲」など
- 名入れ 子どもの名前のみ
祖父母からのお祝いには、祝い膳でお返しします。